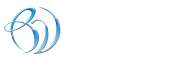ミートホープと食品ブランド
ミートホープの出鱈目ぶりを連日のニュースで見ていると、いくつもの思いや、疑念が湧いて来ます。
- まずはたった百人程度の家族的経営で、役員を含めてこれだけのトップの暴走を諌める人がいなかったのか?何故止められなかったのか?
- 通常極めて品質検査にうるさい生協に納品していたのに、これまで偽装、粉飾が露呈しなかったのはなぜか?
- 行政もかなり前から情報をつかんでいたようであるが、ここまで指導が足りなかったのはなぜか?
1は、製造担当の役員が社長を「天皇のような存在」と表現していた言葉が象徴しているように、絶対的な権力を発揮していたのでしょう。しかしながら、記者会見の席上で「罪を認めてくれ」と訴えたが高額の役員報酬をもらっていた息子、8000万円以上の退職金をもらっていた妻も含め、一人も「こんなことは永く続かない。止めましょう」と言えなかったのでしょうか?雪印のケースも日本ハムのケースも全て告発は内部からです。必ず嘘は露呈します。
2は、筆者はかって食品会社に勤務していて生協の品質チェックの厳密さとしつこさに閉口しながらも、それゆえ「生協ブランド」に信頼を置いていました。その審査を潜り抜けたいたミートホープ社の手腕には驚きました。また、同時にその生協ブランドに疑念を感じました。これも残念なブランドの毀損です
3は産経新聞によれば、「北海道苫小牧市の食肉加工会社「ミートホープ」による食肉偽装事件で、農林水産省と北海道が同社の疑惑に関する告発や情報を昨年少なくとも計4回受けながら、事実を確認できなかったり、告発を放置して偽装を見逃していたことが分かった。報道で表面化するまで1年余の間、行政は368トン以上の偽装ミンチ流通を許したことになる。告発情報の伝達をめぐり農水省と道の説明は食い違いを見せており、責任を押しつけ合う図式になっている。」ようでです。
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/life/m20070702012.html?C=S
この官僚制度がどこまでも綻びかけていることが分かります。綻びどころか、もう裂けているのかもしれないけれど、ことが消費者全般の命や健康にかかわるだけに座視できません。最近では中国産の食材へ疑念が集中していますが、国産品も疑ってかからないといけないようです。
ブランドを構築するにはブランドオーナーの強い思いと、通常は不断の努力やコスト、年月がかかります。ですが結局、ブランドをつくり、育むのは企業のトップを含めて全社員です。コンタクト・ポイントを形成するすべての接点が管理されていないと上手くいきません。目の前の浮利に眼を奪われるとブランドも永らえることはできないのです。ブランドは「信頼」なのですから。
ミートの事業で「希望」を求めた「ミートホープ」社のブランドが悲しい結末を迎えました。